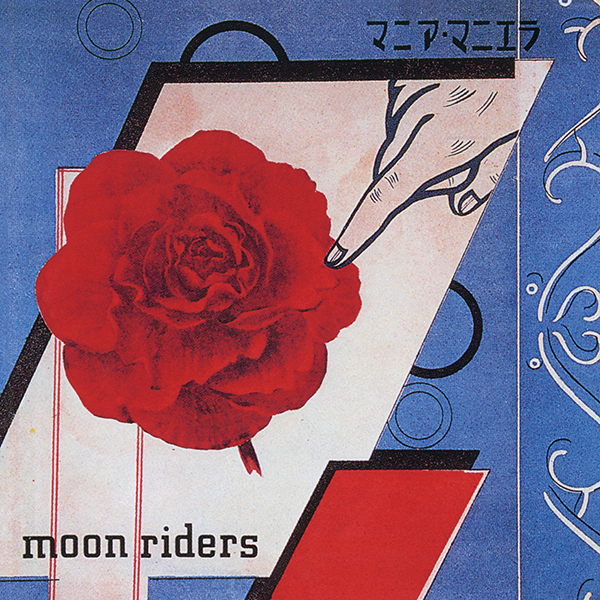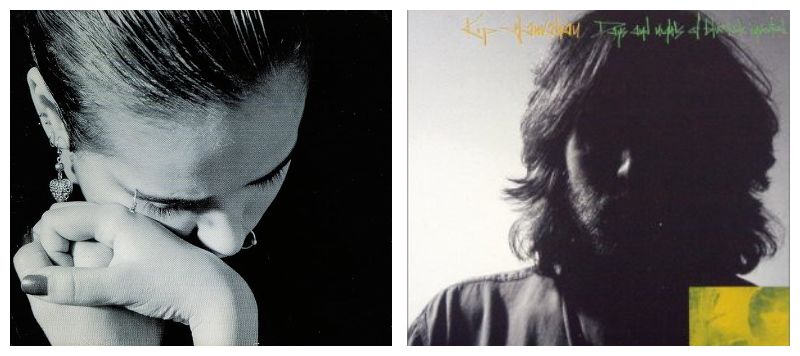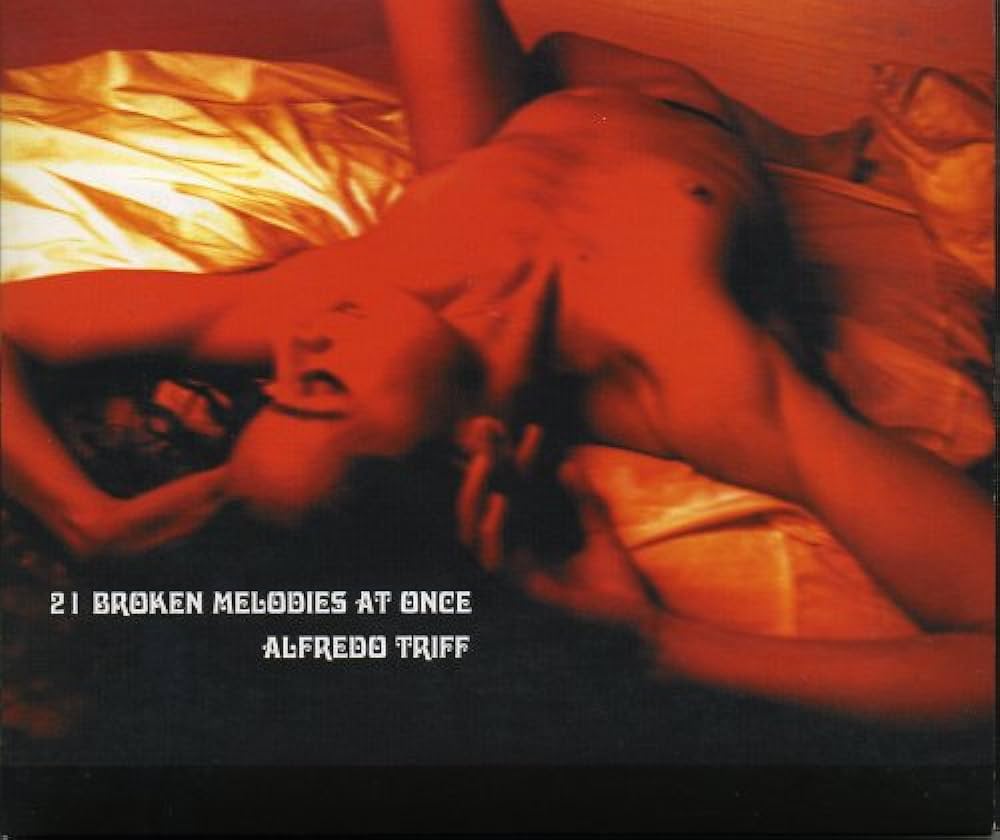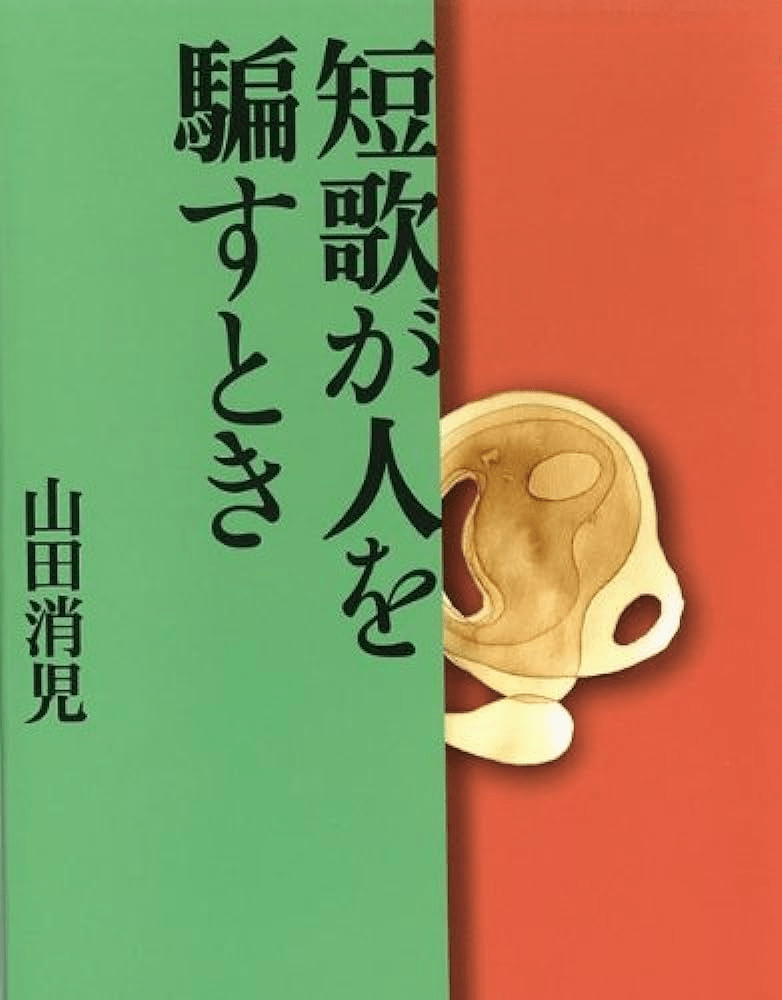
山田消児『短歌が人を騙すとき』
近年のSNS上の短歌ブームが前から気になってて、しかし歌そのものよりは歌に対する評論や分析の方に興味が向いてて、とりわけこの本は短歌の構造そのものに迫ってて面白かった。
俳句・川柳は季語が含まれるが、短歌は含まれない。それによって、俳句・川柳は作者の感情や思惑=「私性」があっても、それは風景なり草花なりに一旦「預けられて」表現されるけれど、短歌はもっとむき出しに「私性」が表現される。それ故に短歌は感傷的な自分語りに過ぎない作品が生み出されがちだとか、作者のキャラクター~プロフィールありきの鑑賞が前提化し過ぎてるといった問題がある……というような指摘が面白かった。
人は短歌を見る時に、書かれていることは「私(作者)」が実際に見聞きし、感じたことをそのまま書いている……ということを無意識に、しかし強烈に前提としながら見ているけど、実際には虚実入り交じった短歌というのは多数あり(兵士としての自身の戦争体験を作品にし、戦地で亡くなったことで知られる歌人の作品の内のいくつかが、まだ戦争に行く前の、戦争映画を観てそれをモチーフにして詠んだ作品が含まれていた、とか)そもそも歌の中に出てくる「私」は「『私』を演じている私」であって、元々フィクショナルな存在なのだ、という話は、自分が普段からラップや歌(短歌ではなく普通に音楽の)について考えていることにぴたっとはまって面白かった。伝統芸能や文学とヒップホップを並べて語るのはあんまり好きじゃない(そういう話をしてる人に対して、文学はともかく、ラップにそんなに興味もなければ聴いてもないんじゃない?と思う場面が多いので……)ですが。この話しだすと長くなるのでまた別の時で。
そもそも自分は歌であれラップであれ、その表現自体の「恥ずかしさ」を一度は自覚しながらも、それをやり続けているような作者の作品が好きなんだなーと改めて感じた。恥ずかしさ、違う言い方をするなら、矛盾といってもいいですが。どんなに「リアル」とか「自然」と言われても「作品として表現」してる時点で全然リアルでも自然でも無くなっちゃうポイントがどこかで出てきませんか?と……それも踏まえてやってる人と、そうでない人とでは、パッと見に同じような作品でも、何かしら決定的な違いがあるように思います。

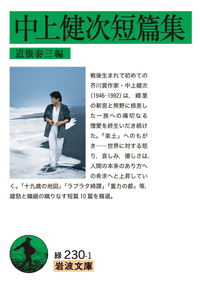
野谷文昭(編)『20世紀ラテンアメリカ短篇選』
道籏泰三(編)『中上健次短編集』
小説って年々読まなくなってる。『ラテン~』の方は、ガルシア・マルケスなど有名な作家からより現代的な作家まで網羅的に紹介されていて面白い。作品ごとに作家のプロフィールも紹介されていて、その作家のラテン文学史における位置づけもわかった上で読めるのが便利だが、ある作家の紹介に『マジックリアリズムの作家としても知られるが、本人はそれを商業的なレッテルでしかないとし、認めていない』という一文があり、渋谷系全盛期の時代にオリジナル・ラブのライブで田島貴男が「俺は渋谷系じゃない!」と叫んだという逸話みたいなことが、マジックリアリズム界隈(?)でも起こるんだと思った。
収録作の中でもベネディッティ『醜い二人の夜』という作品が非常に良かった。それぞれ顔に大きなキズ、火傷を負った若い男女が映画館で出会って……という本当に短い話で、大したことはまったく起こらないんだけど、印象的な終わり方だった。似たようなコンプレックスのある者同士が出会って何かが変わる、という所がぐっとくる。
で、何となく『ラテン~』と続けて読んだら面白いかなと思って選んだ中上健次の方は「十九歳の地図」「ラプラタ」などを含む10編。「蛇淫」の『冷たい熱帯魚』みたいな始まりが面白かった。「十九歳の地図」の徹底的にみっともない、始まる前から何もかも終わってる青春という感じにしみじみと、ああ自分もこういう10代だっ……た……ということもなく、というか年々10代のころ何考えてたかとか思い出せなくなってる。その頃聴いていた音楽や読んでいた本を読んで「何考えてこんなもん見てたんだろう」とよく思う。

マリコ・タマキ / ローズマリー・ヴァレロ・オコーネル『ローラ・ディーンにふりまわされてる』
これは漫画、正確にはグラフィック・ノベル。実写映画化決定~というニュースとともに、作品の存在を知り、タイミングよく手に取ることが出来たので読んだ。全編を通してグレースケールとピンクで構成された色味も美しい。
キャラクターの活き活きした造形が素晴らしいけど、それと同じくらいちょっとした植物や小物類、背景の描き方が素晴らしい。端から見ると虚像のように空っぽに見えるローラ・ディーンに対して、主人公を取り巻く世界の方がよっぽど多彩で豊かに見えるのだけど、そういう対比なんだろうか。恋をすると世界の方が変わって見える、みたいなことなんでしょうか。でもそのローラ・ディーンが最後の最後でああいう表情になる所が良かった。主人公が同性愛者であることが当たり前のように物語が始まりながら、サブエピソード的に物語の途上に出てくる、主人公の友人達に起こる様々なトラブルの描写によって、それ(同性愛者)がまだ当たり前の社会ではないということが「途中」から描かれるのが面白かった。